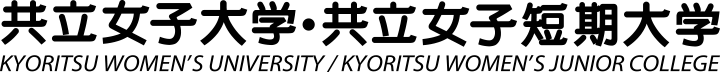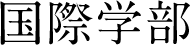Faculty of International Studies
国際学部ニュース詳細
更新日:2025年10月17日
学生の活動
【国際学部】手仕事をめぐる旅~エストニア旅行記~⑤
学生広報委員2年生の西田倫子さんがエストニアに関する記事を執筆しました。
前の記事はこちらからご覧ください。
ーーーーーーーーーー
?Anu Raud(アヌ?ラウド、1943?)さんのアトリエ
【アヌ?ラウドさんとは?】
エストニアを代表するタペストリー作家、手工芸作家。エストニア国内での知名度は高く、昨年幸運にも彼女と出会うことが出来た。
筆者が訪問した時は政府から依頼を受け、子供が学校から出てきてはしゃいでいる様子を描いたタペストリーを制作中だった。
日本でも彼女の作品を紹介する本が出版されている。(アヌーラウド、アヌーコトリ著(林ことみ監修)(2016)『アヌ&アヌの動物ニット:エストニアの伝統柄から生まれた編みぐるみとパペット』,誠文堂新光社)
訪問時、彼女に2024年7月から400時間かけて編んだという眠る鳥のタペストリーや、ヤグルマギクにするつもりが、モチーフが小さくなってしまい、鳥のようになり、"ヤグルマドリ"になってしまった作品も紹介していただいた。とてもおしゃべりなアヌさんによるタペストリー紹介の後、クリスマスツリー代わりのアヌさんオリジナルのクリスマスタペストリーを参加者さん全員と作成した。家の外から取ってきた木の枝を、予め白い布につけられた赤い糸に結びつけるというシンプルな方法である。全ての糸に枝を結び付け終わると完成である。
?クリスマスディナー
エストニアでは、クリスマスにVerivorst(ヴェリヴォルスト)という豚肉の血のソーセージを食べる習慣がある。訪問時に頂いたメニューは、Surtu(スルトゥ)と呼ばれる豚の煮こごり、カボチャなど野菜が入ったサラダ、Kali(カリ)という、黒パンを発酵させたジュース、Grögi(グロッギ)というお酒(訪れた当時19歳だったので私はなし)、イワシ、主食の黒パンだった。
スルトゥは、1年次前期で履修した比較文化入門A(社会生活)の授業で調べてグループでプレゼンテーションをしたことがあり、訪れる前から関心を抱いていた。実際に食べると、なめらかな味でとても美味しく、好みの味だった。
ヴェリヴォルストはこの時、2種類のメーカーのものが用意されていたので、食べ比べしたところ、食感に大きな違いがあった。 しかし、どちらも独特の臭みもあまり感じず、臭み消し用のジャムを使わずに食べられた。とても美味しかったので余った分まで頂いてしまった。カリは日本で例えるなら、炭酸が抜けて、少し甘さが落ち着いたコーラのようであった。
ゲストハウスの方の話によると、エストニアではクリスマスの日は、朝から料理を準備し、オーブンをかけてから教会へ行き、家に帰ると事前に焼いたヴェリヴォルスが出来上がっている。そして、クリスマスイブは家族と過ごし、翌日の25日は親戚などに会いに出かけに行くのが一般的だそう。
ディナーの後は、ツアーの参加者さん達とジンジャークッキーを作った。
エストニアでは、ジンジャークッキーはクリスマスの定番で、毎年シーズンになる至る所で販売されている。
.jpg)
【ヴィリヤンディ市街地散策】
ヴィリャンディにはいちごのオブジェが合計8個、その他車止めとして作られた猫のオブジェ、昔の市長やこの町出身の芸術家といったこの街で活躍した人物の銅像など、色々なものが街のあちこちに置かれているため、散歩のついでに見つける楽しさがある。ガイドさんと説明板によると、いちごのオブジェが8個も街にあるのはヴィリヤンディ出身の画家Paul Kondas(パウル?コンダス) (1900-1985)の美術館(KONDASEKESKS,KONDASCENTRE)があること、実際にいちごを栽培していることもあり、ヴィリャンディの知名度をあげることを目的におかれたという。
コンダ美術館前にあった説明板。彼の作品に「Maasikasööjate(英Strawberry Eaters)」がある。この作品が、オブジェを置くきっかけになったことが説明されている。
.jpg)
街を抜けると、城跡が現れる。
エストニアの観光案内の公式ホームページによると、この城は13世紀に、エストニアの要塞に作られたが、スウェーデンとポーランドとロシアとの戦いが原因で大部分が破壊され、今日では僅かな石壁が残ってるだけである。既に20世紀の初めには、この城跡はヴィリャンディの住民への娯楽地に変化していた。
.jpg)
次回に続く